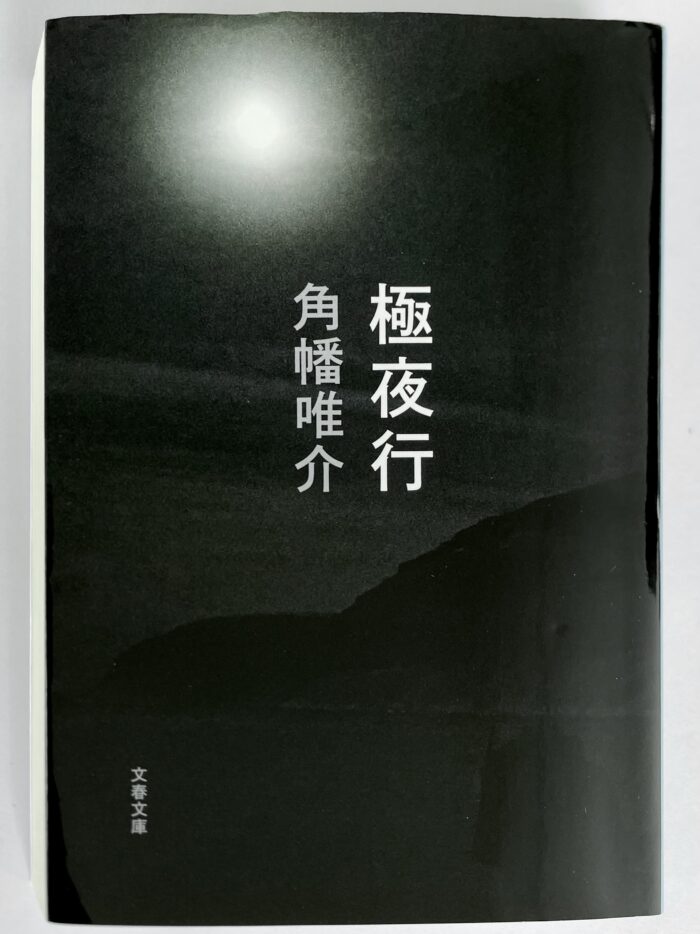
これぞノンフィクション
この本を手に取ったきっかけは、本屋で何気なく書棚を見ていて作者の“角幡唯介”という名前が目にとまったから。
何年か前に、角幡氏の著書『空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む』を読んだことがある。角幡作品のノンフィクションとしてのリアルさを知っていたこともあってふと手にした『極夜行』だが、実際に読んでみると没入感や疑似体験度は『空白の五マイル』よりも数段パワーアップしているように感じた。
文庫本の帯にあるキャッチコピーは、
― ひとり極夜を旅して、四ヵ月ぶりに太陽を見た。―
これだけ見ると、「“ずっと夜の世界が続いた後に出てきた太陽を見て感動した”みたいな話か」などと、まだ読んでもいないのに内容をザックリまとめたくなるが、本書は決してそんな単純な作品ではなかった。
極夜というのは、ただ太陽が出ないだけじゃない。
作中で「命にかかわる暗さ」と表現されている、中央高地を超えたグリーンランド北側に広がる異次元の闇。宇宙空間が地表まで降りてきたかのような極寒。そうした環境下で延々と続く氷に覆われた世界を一人で移動するうちに変化していく精神状態。
もちろん、現実ではどれ一つとしてそれに近い経験すらしたことがない。それなのに、自分もまるでその場にいるかのように体の芯まで冷え切った感覚になる。極夜の世界を妖しく照らし出す月の光に惑わされ、見えていないのに見えているように錯覚させられ、希望と怒りと絶望を順繰りにループする筆者の精神を読者も疑似体験させられる。これこそ、まさにノンフィクションの醍醐味だ。
光のない世界=人類の知らない世界
作中で特に印象に残った言葉がある。
シオラパルクを出発してから一か月少し経った時、とある理由から内陸の湿地帯へと踏み込んでいった際に、筆者が「地球上の風景のレベルを超えた」と描写する景色を目にした時の様子を説明した言葉だ。
“この景色を見たとき、私は、私たちが知っている地球の裏側にあるもう一つの地球、太陽が常に存在する私たちの住むシステムの外側に人知れず存在してきた地球の別位相に入り込んだのを感じた。
すなわち極夜の内院である。”
“極夜の内院”っていう言葉には、一度聞いたら忘れられない響きがある。
確かに、私たちが普段意識している世界というのは太陽=光があることが絶対の前提条件となっている。時計があろうがなかろうが、太陽が毎日昇ってくるからこそ1日24時間という単位を肌感覚として認識できる。その光が何か月もなくなる環境というのは、筆者が言うように人類が知らないまさに別位相の世界であり、それこそ太陽系の端っこで光が十分に届かない天王星のような別の惑星の話に近いわけだ。(ちなみに、天王星は自転軸がズレまくっている上に公転周期が84年もあるせいで、極点では極夜と白夜が42年ずつ続くとか。)
こう書くと、息が詰まりそうな緊張が続く作品なのかと思うかもしれないが、旅の相棒であるウヤミリックと名付けられた犬とのやり取りでは極限の状況下なのにクスッと笑えるようなシーンもあり、『極夜行』全体を通して絶妙なアクセントとなっている。しかし、それはペットの犬に癒されたなんていう表面的なものではない。橇(そり)を曳くという、ペットとは大きく異なる存在である労働犬と人の関係においては、生と死をかけた原始的な意味でお互いに依存しているのだ。その辺りの詳細は、実際に本書を読んで味わってみて欲しい。
スポンサーリンク
作品情報
タイトル:極夜行
著者:角幡 唯介
第45回大佛次郎賞受賞作
レーベル:文春文庫
出版社:文藝春秋
発売日:2021年10月10日
ISBN: 978-4-16-791772-2
あとがき
これまでにも、当ブログで何回か書評を書いてみたことがある。かなり時間をかけて作品の世界観や文学技法なども考察しながら記事を作ってみたものの、何かしっくりこなかった。アカデミックな視点からの文学作品の分析みたいになっているからかもしれない。好き放題言う毒舌書評みたいなのも読む側としては面白くて好きなのだが、自分ではどうもそういったモードで書ける気がしない。
なので、ここはやはり本を読むのが好きだという原点に立って、自分が読んで素直に「読んでよかった」と思えた作品を難しいことを考えずに紹介していこうと思う。そんなわけで、気分を新たに紹介したい作品の一番目として今回は迷わず『極夜行』を選んだ。これからも、コーヒーをゆるりと飲みながら気分よく読める&個人的に好きになった作品をピックアップしていきたい。




