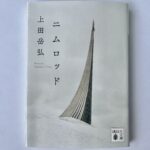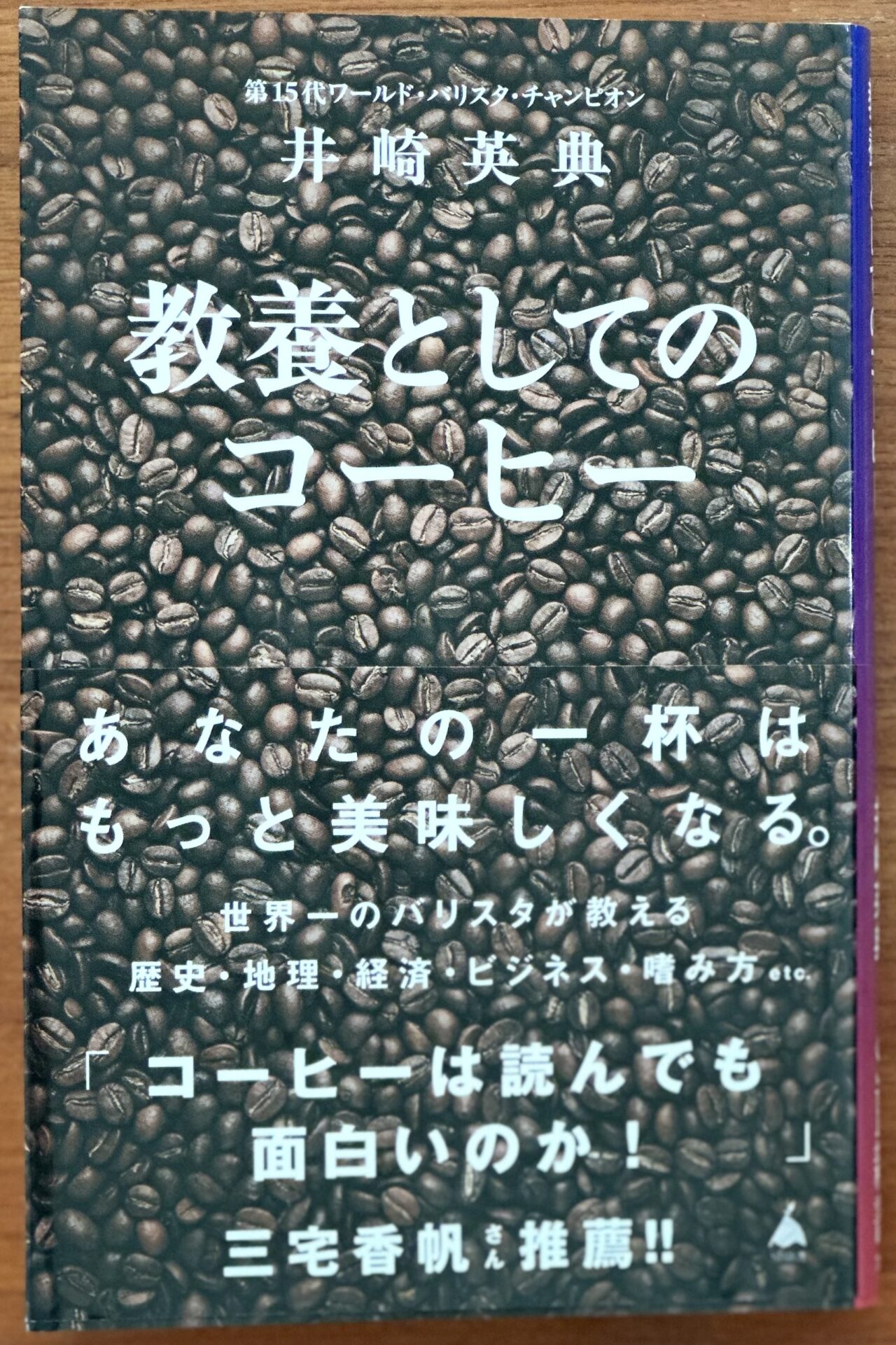
今まで読んだことのないディープさだった
コーヒーが人生に欠かせない私は、これまでコーヒーに関する本や雑誌はそれなりの数を読んできた。
そうした読み物には、専門的な内容でコーヒーの起源や品種について詳しく説明されているものも少なくない。ただ、そこそこ知識が身についてくると、新しい本を読んでもすでに知っている情報の比率が高くなる。ここ最近は、どのコーヒー本を見ても似たり寄ったりの印象を受けるようになってしまい、本屋で手には取っても結局買わずに棚に戻すことが多かった。
そんな背景もあって、最新入荷の棚に『教養としてのコーヒー』を見つけて手にした時も、最初は正直あまり期待していなかった。それなのに、とりあえず見ておこうかとパラパラとページをめくりはじめると、今まで読んできたコーヒー本とは大きく違う内容に目が離せなくなった。
もちろん、本書でもコーヒーの発祥や起源、どうやって世界中に広まったかなどのよくある定番知識も扱われているのだが、それを説明する視野と分析の広さ、情報のディープさがケタ違いなのだ。
コーヒーと国際政治の意外な関係
例えば、1章では「ブラジルが最大の生産国になった理由」という見出しがある。
どの本でも、ブラジルの植民地時代にコーヒーが持ち込まれて、栽培に適した土地だったため大規模農園が国中に広がっていった、といった程度の情報は載っている。しかし本書は、ナポレオンが出した「大陸封鎖令」を中心に、フランスとイギリスの緊張関係、それがコーヒーと砂糖に及ぼした影響、ナポレオンに攻め込まれたポルトガル王族のブラジルへの亡命とそこからコーヒー栽培が加速する流れなど、ここだけで2ページを割いてさまざまな角度から“なぜブラジルがコーヒー生産量1位になったのか”を説明している。
まさかこんなところでバリバリの国際政治が出てくるとは思わなかったが、いやぁ、とにかく面白い。この見出しの中身だけでも、今まで知らなかったことがてんこ盛りだった。
その他にも、セブンイレブンの100円コーヒーとマクドナルドの100円コーヒーとでは、どのように全く異なる開発アプローチをしているのか、といった普段あまり考えることのない(知ることのできない)切り口が散りばめられているのも本書の魅力だろう。
さまざまなコーヒーコンサルティングの案件を手がけている著者ならではの具体的事例や経験を数多く紹介しつつ、随所にプチ豆知識のスパイスも効かせながら、私たちが日常で何気なく接しているコーヒーの裏側に広がる世界を見せてくれる。まさに“教養としてのコーヒー”というタイトルがしっくりくる本だ。
スポンサーリンク
バリスタ=“コーヒーの編集者”
2014年のWBC(ワールド・バリスタ・チャンピオンシップ)優勝者である著者の井崎氏は、「バリスタとは何か」という問いに対して“コーヒーの編集者”であると答えている。バリスタのコーヒーに関する知識や抽出技術が優れているのはもちろんだが、井崎氏によると、結局のところバリスタの価値は「コーヒーを味わう体験をプロデュースすること」にあるという。
そう言われてみると、確かに世界のトップレベルのバリスタはコーヒーの魅力を色々な形で発信することによる自己表現がうまい。コーヒーの生産に関わる多種多様なプロジェクトを立ち上げるバリスタもいれば、家庭で非常に高いレベルの焙煎や抽出を楽しめる独創的なコーヒー器具を開発するバリスタもいる。
しかし日本人の場合、技術を突き詰めたり正確さを極めたりするのは得意だが、自己表現というのはどちらかというと苦手な部類に入ることが少なくない。この点で著者は、日本人として「日本的な美意識を取り入れたコーヒー体験を作ることが強みのひとつになる」と書いている。そのあたりの詳細も、ぜひ本書を読んで確かめて欲しい。
コーヒー業界のネガティブな側面も
本書を読んでいて感じた点の一つは、コーヒーに関わるネガティブな面についてもかなりストレートに書かれているということだ。
例えば、消費者としても何となくピンとくることがあるが、お店でコーヒーを飲んだ時に「以前はもっと美味しかったような気がする」というケース。もちろん単なる勘違いの場合もあるだろうが、価格は変えていないものの品質を少し落とした「サイレント値上げ」の可能性について取り上げている。著者自身、「飲んでいてサイレント値上げを感じることが多くなってきた」とぶっちゃけているのだ。
また、これはプロの仕事だと誰もが考えるカッピングの世界についても、「いいかげんなことをいう人も中にはいる」「そもそもカッパーとしての能力に疑問符がつく人もいる」と厳しい言葉が。これは別に嫌味を言っているわけではなく、買い付けのための客観的な品質評価が必要なカッピングにおいて主観的な評価をすることの問題点を指摘している文脈だが、一般人が接することのない内情を知ることができて興味深いと感じた。
もう一つ、本書では最近市場での取り扱いが増えてきている「インフューズドコーヒー」についての懸念も挙げている。
生産処理の新しい方法として「アナエロビック」発酵や「カーボニックマセレーション (CM)」などの手法が開発され、強い果実味を含むこれまでにない独特な風味や味わいが消費者の人気を集めてきたが、これらはあくまで天然の発酵プロセスにより作り出される風味特性だった。ところが、最近は人工的にフルーティーな香りを付けた「インフューズドコーヒー」が流通するようになっている。「マンゴーのような香り」がするコーヒーを作りたいから本物のマンゴーを混ぜてしまおう、という手法が取られているわけだ。
もちろん、インフューズドコーヒー自体が悪いわけではない。ただし著者は、「インフューズドコーヒーの一部は、人工的な香り付けであることを隠して売られている」「まるで生産処理により生まれた自然な香りとして消費者に誤解させるのは悪質」と述べ、今後さらにインフューズドコーヒーの製法の実態確認と情報開示をさらに進める必要がある、と結んでいる。消費者に勘違いさせるような売り方が見られるにもかかわらず、それを規制する仕組みがない現状に警笛を鳴らしているのだ。
上に挙げたようなコーヒー業界が抱えるネガティブな面をオブラートに包まず発信することに、同じ業界に身を置くものとしては色々なしがらみもあるだろうし躊躇する人がいたとしても不思議ではない。そんな中、スペシャルティ―コーヒー協会 (SCA) の理事も務める著者が、こうした課題を避けることなく鋭く切り込んでいる点も本書の価値を増している。
まあ難しいことは別にして、読み終わると質の高い講義を受けたような充実した気分になった。文芸評論家の三宅香帆氏が書いているように「一杯のコーヒーには歴史と文化史が詰まっている」ということを深く実感させてくれる本なので、コーヒー好きの方にはぜひ手に取って欲しいと思う。
スポンサーリンク
作品情報
タイトル:教養としてのコーヒー
著者:井崎 英典
出版社:SBクリエイティブ
発売日:2025年9月15日
ISBN: 978-4-8156-3604-3